スティンザー効果とは、会議や打ち合わせなどで複数の参加者が1つのテーブルを囲むとき、座る位置によって相手に与える印象が大きく変わるという興味深い現象を指します。実は、皆さまも日常的にこの効果を体験しているかもしれません。例えば、上司やクライアントとのミーティングで「どこに座ろうか」と迷った経験はありませんか。そしていったん座ってみると、なんとなく「そこの席では話しづらい」「相手との距離が遠いと感じる」など、微妙な違和感を覚えたりすることがあります。こうした“座る場所”がもたらす影響に、実は心理学的な裏付けがあるのです。
スティンザー効果のポイントとして、座る位置は単に視線や声の聞こえ方を変えるだけではなく、相手から受ける「どういう人だろう」という第一印象や、そこから生まれるコミュニケーションのしやすさまで変えてしまいます。特に、20代から30代の会社員の方々が出席するような会議では、まだ顔なじみが少ない人と一緒になる機会も多いかもしれません。そんなときに活かせるのが、このスティンザー効果の知識なのです。
座り方による印象の変化
座り方による印象の変化は、いくつかのパターンがあります。例えば、会議テーブルの正面に座れば、相手に対して「意見をぶつけあう」ような形になることが多く、気持ちとしては対立関係が生まれやすいとされます。一方、斜めに座ると、お互い同じ空間を共有している気持ちになりやすく、相談しやすい雰囲気になるといわれています。また、横並びだと「親密さ」が増し、一緒に作業や議論を進める“仲間”感が出やすい傾向があります。こういった座る位置の違いが、会議の雰囲気や成果にも影響を及ぼすというのがスティンザー効果の本質です。
しかも、この効果は話す内容だけでなく、相手に対する印象や説得力にも関与します。たとえ同じ発言をしていても、自分が座る位置一つで「もっと詳しく話を聞いてみよう」「この人は頼れそうだ」などと思わせることもできれば、その逆もあり得るわけです。「大事なプレゼンのときになんとなく人がこちらを見てくれなかった」「緊張してしまって声が通らなかった」というとき、実は選んだ席の位置も一因だったかもしれません。
では、具体的にどのようなエピソードでこのスティンザー効果が発揮されるのか、ここから3つのケースを紹介します。
エピソード1:ミーティング開始直後の微妙な沈黙
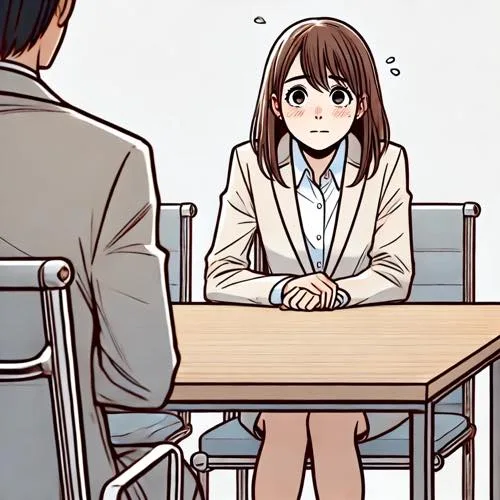
新入社員として初めて先輩方と同席する会議。席に着くと、端のほうで何だか周囲の会話に入りにくい雰囲気を感じる。自分が口を開いても周りの視線や声が届かず、「え、もう一度いいですか?」と聞き返されたりする。気まずさを取り除こうとさらに一生懸命声を張るが、今度は会議の進行を止めているのではと心配になり、ますます発言がしづらくなってしまう。そんな経験をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。
これは新入社員にかぎらず、他部署から初めて来た人や外部の取引先担当者などにとっても同様に起こりやすい事例です。多くの場合、会議室に入りやすいドア近くの端や、誰も座っていない奥のほうの席を選びがちですよね。しかしそうすることで、既にコミュニケーションが形成されているグループの中心からさらに距離が生まれ、結果的に発言や話を振ってもらう機会が少なくなるというスティンザー効果が発揮されてしまいます。もちろん、無理に真ん中に座ればいいというわけではありませんが、最初は緊張していても「相手と自然に目が合う席」に座るほうが、周りに自分の存在をスムーズに認識してもらいやすいのです。
エピソード2:希望部署との面談

社内で異動を希望する際、面談をすることになったが、とにかく緊張が止まらない。相手は普段なかなか接点をもてない部長クラスで、いきなりの面談は相当にプレッシャーがかかる。いざ面談室に入ると、意識する余裕もないまま、とりあえず部長の正面に座る。しかし正面に座ったことで、相手と対峙しているような雰囲気が強まり、こちらも表情が硬くなって余計に口数が少なくなってしまった。面談が終わってから「もうちょっと笑顔で話せばよかった」「自分のことをちゃんと伝えきれなかった」と後悔してしまう――そんなエピソードもよく耳にします。
面談の場面では、自分をアピールしたい一方で、相手にもリラックスしてもらいながら話を進めたいものです。けれども正面に座ってしまうと、どうしても“向かい合う”構図が強くなり、相手の反応を逐一自分の正面から受け止める形になります。もし少し席をずらせる状況なら、テーブルの角を挟んで斜めに座るようにするだけでも印象が変わります。斜めの位置関係は「同じ視点を共有できる仲間」感を相手に与えやすいため、面談が対立ではなく対話の場になる可能性が高まります。このちょっとした座り方の工夫こそがスティンザー効果をうまく利用するコツです。
エピソード3:大事なプレゼンでの指名
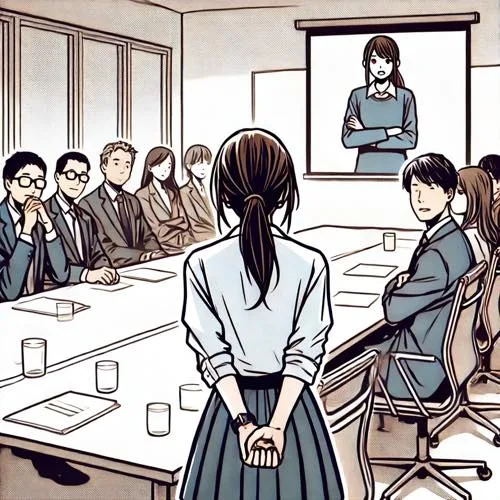
あるプロジェクト会議で、プレゼンターを急遽任されることになった方がいました。前に出て資料を説明するだけではなく、座っているメンバー同士でも議論を深めようという形式だったため、その方はプレゼン後に自席へ戻ってディスカッションに参加しました。ところが戻ってみると、自分の席が会議テーブルの端で、話の中心から外れた場所。いざ質問や意見を求めようとしても、声が全員に届きにくく、また視線の合う相手が限られるため、積極的に質問を振ってくれる人も少なくなってしまったのです。結局プレゼンに関する細かい疑問点が共有されないまま話が進み、「内容は悪くなかったのに、いまいち盛り上がりに欠けたな」という印象になったそうです。
大事な場面こそ、スティンザー効果を意識すると大きな差が出ます。ディスカッションを円滑に進めたいなら、できる限り集団の視界の中心に位置しやすい席を選ぶとよいでしょう。もし会議が自由席に近い形であれば、プレゼンを担当する人はあらかじめ会場全体が見渡せる席を押さえておくと、意見交換の際に多くの人と目が合い、議論をリードしやすくなります。ちょっとした座る位置の違いが、プレゼン後の場を温められるかどうかに直結するのです。
スティンザー効果の活用方法
スティンザー効果を最大限に活用したいとき、まず重要なのは「自分が何を求めているか」をはっきりさせることです。話し合いの中心になりたいのか、それとも相手と対立構造を避けながら相談する形を取りたいのか。例えば、自分の意見を強めにプッシュしてリーダーシップを発揮したいなら、会議テーブルの正面や中心に近い席を選ぶのも一つの手です。一方、相手から自然に相談を引き出したい場合は、正面から少しずれた斜めのポジションが有効です。完全に横に座れば、さらに親近感を高め、協力的な姿勢を演出することができます。ただし、仲良くなりすぎるのではなく、適度な距離感を保ちたいときには正面寄りだけれど完全には対峙しない、というように位置取りを微調整するとよいでしょう。
また、座る位置だけでなく、座り方や体の向きによっても印象は変わります。どんなに斜めに座っていても身体ごと背けてしまえば、「話をあまり聞いていないのでは?」というネガティブな印象を相手に与えてしまいかねません。逆に正面であっても、少し体を前に傾けたり、目線を合わせて頷いたりすれば、積極的に話を聞く姿勢が伝わります。要は、座る位置と合わせて身体の向きや視線をセットで考えることが肝心なのです。
すぐに実践できるアクションプラン
スティンザー効果は、言葉だけでなく無言のうちに交換される印象にも影響します。明日からでも実践できる小さなステップとして、最初に会議室へ入る際、「今日はどんな目的で参加するのか」「どのように周囲と関わりたいのか」を頭の中で整理してみてください。もし活発に意見を出したいなら中心に近い席を、相手の話を引き出しながらサポートしたいなら斜めが向かい合う席を選ぶ、といった具合に、一度考えてから席に向かうだけで大きな違いが生まれます。さらに、座ったあとも自分がどの方向を向いているか、相手とどれくらい目が合っているかを意識してみましょう。そうすることで、自然と自分の声量や相槌の回数にも変化が出てきて、会議の流れや雰囲気をリードすることができます。
最後に
スティンザー効果は、会社員の皆さまが普段の会議や面談、プレゼンテーションの場面などで簡単に取り入れられる心理テクニックです。座る位置を少し変えるだけで印象が大きく変化し、その後のコミュニケーションがスムーズになったり、自分の意見がより通りやすくなったりします。特に20代から30代の方にとっては、組織内での立場や役割が変わっていく大切な時期だからこそ、自分の存在感を示すうえでもこの効果を上手に使ってみてください。慣れてしまえば難しいことは何もなく、「今日はどの座り方で臨もうかな」とちょっと意識するだけで大丈夫です。
スティンザー効果を理解しておけば、これから先のキャリアにおいて、様々な場面で応用できるはずです。たとえば取引先との商談でも、相手がリラックスしつつ話がしやすい配置をあらかじめ考えておくことで、商談のスムーズな進行に役立ちますし、お互いにメリットが大きくなるでしょう。「座る場所」一つとっても、ほんの少しの工夫が長期的に見ると大きな結果を生むことがあります。今日お伝えしたエピソードや考え方をぜひ参考にしながら、次の会議や打ち合わせから実践してみてください。きっと、その違いに気づいて驚くことと思います。スティンザー効果を味方につけて、今以上に円滑でポジティブなコミュニケーションを楽しんでいただければ幸いです。

