リーダー会議や友人とのグループ旅行計画で、「どうしてこんな大胆な決断をしたんだろう?」と思った経験はありませんか?それは、心理学における「リスキー・シフト」という現象が関わっているかもしれません。この現象は、集団での意思決定において個々のメンバーよりもリスクを取る方向に偏ることを指します。リスキー・シフト効果について理解を深めることで、職場や日常の意思決定のあり方を見直すきっかけとなるかもしれません。
リスキー・シフトとは?
リスキー・シフト効果は、個人での意思決定に比べて、グループで意思決定を行うとき、よりリスクを取る方向に決断が偏ることを意味します。なぜ集団になると、私たちは思い切った判断を下す傾向があるのでしょうか?これには、いくつかの心理的な要因が絡んでいます。
一つは責任の分散です。集団で意思決定を行うと、一人ひとりが責任を感じにくくなり、「もし失敗しても自分のせいじゃない」と考えがちです。また、グループ内の議論で意見が強調されていくと、メンバーたちがその意見を支援する形でリスクが増大する傾向があります。さらに、グループ内の他のメンバーの賛成が、自分の選択に対する自信を強め、より大胆な決断を促すこともあります。
エピソード1:新規プロジェクトの決断
まず、リスキー・シフトの一例として職場での新規プロジェクトの立ち上げを考えましょう。ある会社で、複数のチームメンバーが新しい製品の開発に挑戦するかどうかを議論していました。メンバーの中には、競合も多く、リスクが大きいと慎重になる人もいましたが、話し合いが進むうちに「みんなでなら成功できる」とのムードが強まり、結果として予想よりもリスクの高いプロジェクトに着手することに決まりました。この結果、メンバーは全体としてのリスク感覚が薄まり、個々の慎重な意見が埋もれてしまったのです。

エピソード2:友人との旅行計画
次に、友人グループでの旅行計画の話です。あるグループが休暇を利用して海外旅行に行くか、国内旅行にするかを話し合っていました。最初は多くの人が費用や安全性を考慮して国内旅行を提案しましたが、一部のメンバーが「せっかくの休みだから思い切って海外に行こう」と言い出すと、次第に他のメンバーも「それもいいかもしれない」と意見を変えました。結果として、当初の予定よりも高額でリスクのある海外旅行が決まりました。グループの勢いに飲まれて、慎重さが後退し、最終的にはリスクを受け入れる方向に全員が傾いたのです。
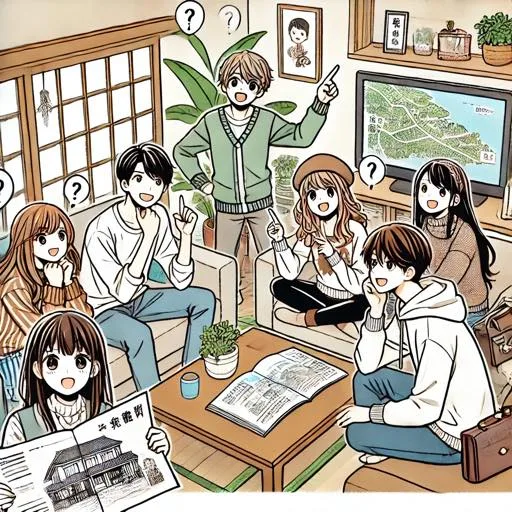
エピソード3:投資における判断
最後に、投資の意思決定における例を挙げましょう。あるグループの友人たちが一緒に資産運用を始めることにしました。個々のメンバーは比較的保守的な投資先を検討していましたが、グループディスカッションが進むうちに、リターンが大きいがリスクも高い新興市場への投資が魅力的だという意見が強まっていきました。最終的に、グループ全体でリスクの大きな投資に踏み切ることが決まり、リスキー・シフト効果が見事に働いた結果となったのです。

リスキー・シフトのメリットとデメリット
リスキー・シフトにはメリットとデメリットの両方があります。
メリットとしては、集団での大胆な決断が新しい挑戦やブレイクスルーを生むことがあります。例えば、企業が大胆な新製品をリリースすることを決断した際、それが市場で大成功する可能性もあります。個人では躊躇してしまうようなリスクを、集団で取ることで大きな成果を得られる場合もあるのです。
一方で、デメリットとして、無謀な決断により失敗のリスクが増大することが挙げられます。特に、責任が分散されることによって個々のメンバーが深く考えずにリスクを取ることになり、結果として大きな損失を被る可能性もあります。リスキー・シフトは、特に集団の結束が強く、他者の意見を強く支持する傾向がある場合に顕著に現れやすいです。
リスキー・シフトを回避する方法
リスキー・シフトのリスクを避けるためには、いくつかの対策があります。
まず、集団での意思決定の際には、全員が率直にリスクについて発言できる環境を整えることが大切です。反対意見を持つメンバーが安心して意見を述べられる雰囲気を作ることで、偏ったリスクテイクを避けることができます。
また、意思決定の前に、個々のメンバーが独自に考えた意見を事前に集めておくことも有効です。これにより、集団での討論が始まる前に個人の慎重な視点を確保することができます。さらに、第三者のアドバイザーを導入することで、冷静な意見を取り入れ、集団が過剰なリスクを取らないようにすることも一つの手です。
まとめ
リスキー・シフト効果は、私たちの日常生活や職場における意思決定に大きな影響を与える可能性があります。集団での決断がリスクを取る方向に偏ることで、新しい挑戦を生む可能性がある一方で、無謀な決断により失敗するリスクも伴います。この効果を理解し、適切な対策を講じることで、よりバランスの取れた意思決定ができるようになるでしょう。次回、集団で重要な決断を下す場面に直面したときは、ぜひリスキー・シフトの存在を念頭に置き、慎重に判断してみてください。

