クローズドクエスチョンとは、「はい」か「いいえ」など限定的な答えが求められる質問のことです。例えば、「今日は雨ですか?」のような質問がクローズドクエスチョンにあたります。一見すると単純に思えるこの質問スタイルには、実は強力な効果が隠されています。特にビジネスシーンや職場でのコミュニケーションにおいて、クローズドクエスチョンを上手く活用することで会話の流れを効果的にコントロールし、相手に負担をかけずに意思疎通を図ることができます。
この記事では、クローズドクエスチョンの実際の活用場面とその効果について深堀りし、あなたの日々のコミュニケーションスキルを劇的に向上させるためのヒントを紹介します。具体的なエピソードを交えながら、すぐに実践可能な方法を探っていきましょう。
エピソード1: 会議での時間管理
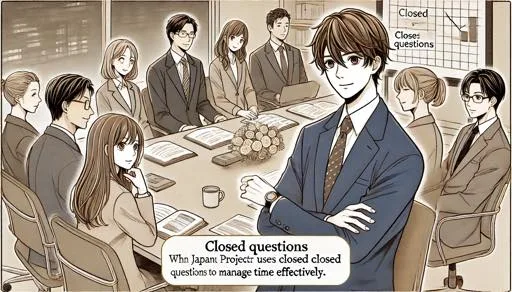
あるIT企業でプロジェクトマネージャーを務める健太さんは、いつも会議が時間通りに終わらないことに悩んでいました。参加者全員が意見を述べたがり、特にオープンクエスチョン(自由回答が可能な質問)ばかりが飛び交うため、会議が予想以上に長引くことが多々あったのです。しかし、健太さんはある日、クローズドクエスチョンを活用することで状況を劇的に変えることに成功しました。
例えば、進行中の議題に対して「この方法で進めて問題ないですか?」とクローズドクエスチョンを投げかけることで、参加者に「はい」か「いいえ」で答える選択を促しました。結果として、無駄な議論が減り、重要なポイントだけが整理されるようになりました。健太さんは「短い時間で要点をまとめる力がついた」と語り、その後も積極的にクローズドクエスチョンを使うようになったと言います。
エピソード2: 部下へのフィードバック
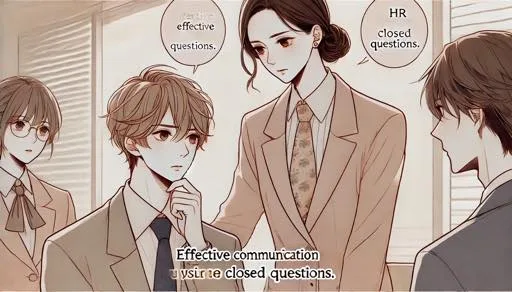
次に紹介するのは、人事担当として働く美咲さんのエピソードです。美咲さんは、若手社員へのフィードバックをする際に、相手がどう受け止めているのか分からず、コミュニケーションの難しさを感じていました。多くの部下は、オープンクエスチョンに対して答えるのが苦手で、何を言ったらいいのか迷うことが多かったからです。
そこで美咲さんはフィードバックを行う際に、次のようなクローズドクエスチョンを使うことにしました。「今回のプロジェクトの進め方について、不安に感じる部分はありましたか?」という質問です。この質問は、相手が「はい」か「いいえ」で答えやすく、具体的なポイントがある場合はその後に補足ができるような流れになっています。
この方法により、若手社員たちは自分の考えを表現しやすくなり、美咲さんは「相手の感情を読み取り、的確にサポートできるようになった」と実感しています。また、答えが限定されることで、無駄な説明が減り、お互いのコミュニケーションがよりスムーズになったのです。
エピソード3: クライアントとの交渉
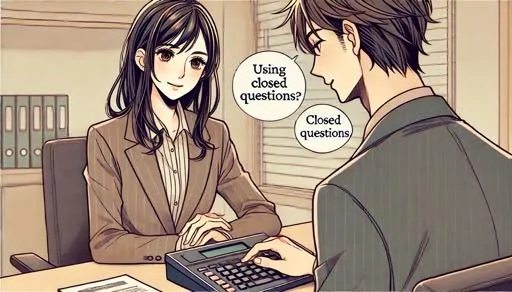
営業担当の裕樹さんは、クライアントとの商談でクローズドクエスチョンを効果的に使うことで、契約率を上げることに成功しました。以前の裕樹さんは、相手のニーズを探るためにオープンクエスチョンを多用していましたが、それでは具体的な回答が得られず、商談が長引くことが多かったのです。
そこで裕樹さんは、「このプランでご満足いただけるでしょうか?」というようなクローズドクエスチョンを活用し、相手が簡単に答えを出せるように促しました。この質問により、クライアントは自分の考えを整理し、次のアクションに対して意思を示しやすくなります。結果として、商談が短時間でまとまり、契約に至るケースが増えたのです。
クローズドクエスチョンの活用方法
クローズドクエスチョンを使うと、相手に負担をかけずにコミュニケーションを進めることができます。例えば、会議の場では議論が発散しないように、要点を絞るためにクローズドクエスチョンを使うと効果的です。また、部下へのフィードバックやクライアントとの商談においても、相手が答えやすい形で質問を投げかけることで、スムーズに話を進めることができます。
クローズドクエスチョンは、以下のようなシーンで特に役立ちます。
- 会議での時間管理:議論をまとめ、決定を促すために「この方法で進めて問題ありませんか?」と聞くことで、無駄な議論を避けられます。
- フィードバックの効率化:相手が迷わず答えられるように「この部分で困ったことはありましたか?」とシンプルに質問することで、効果的なコミュニケーションが図れます。
- 交渉の加速:相手の意思を引き出すために「この提案に納得いただけますか?」と質問することで、次のアクションに移りやすくなります。
すぐに実践できるアクションプラン
クローズドクエスチョンを使いこなすためには、まず日常的にこの質問の形式に慣れることが重要です。例えば、次のようなシンプルなアクションプランを試してみましょう。
会話の中で一つのクローズドクエスチョンを取り入れる:例えば、ランチの際に「今日はパスタで良いですか?」と同僚に聞くなど、日常的な場面で小さな実践を繰り返してみてください。これにより、クローズドクエスチョンの使い方に自然と慣れていくことができます。
会議の議題ごとに決定的な質問を用意する:次の会議で、一つの議題についてはっきりと決定を促すクローズドクエスチョンを準備しておきましょう。例えば「この方向性でプロジェクトを進めることでよろしいですか?」といった質問をあらかじめ考えておくことで、議論の行き先を明確にし、効率的に会議を進行できます。
部下との面談で不安要素を確認する:フィードバックの際に「この点について問題を感じましたか?」と質問することで、相手が答えやすくなり、本音を引き出しやすくなります。これにより、相手が感じている問題点を明確にし、解決への道筋を立てやすくなるでしょう。
まとめ
クローズドクエスチョンは、相手に考えさせすぎず、簡潔に答えを得るための強力なツールです。特にビジネスシーンにおいては、時間管理や効果的なフィードバック、そして交渉の成功率を上げるために大いに役立ちます。オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを使い分けることで、あなたのコミュニケーション能力は飛躍的に向上し、職場での信頼を得ることができるでしょう。
今日から、クローズドクエスチョンを使って、効率的で的確なコミュニケーションを目指してみてください。会議や交渉、日常の会話において、このシンプルな質問形式が、あなたの思いを伝え、相手の反応を引き出す助けとなるはずです。

