ツアイガルニック効果とは?
ツアイガルニック効果とは、心理学者ブルーマ・ツアイガルニックが提唱した現象で、「人は未完了のタスクや中断された物事をより記憶に残しやすい」というものです。完了しているタスクよりも、途中で中断されたタスクの方が、脳に強く残り続けるのです。
この効果を利用することで、目標達成やモチベーションを高める手助けができます。例えば、仕事のプロジェクト、家事、学習の計画など、あらゆる場面で活用可能です。それでは、日常の中でこのツアイガルニック効果を感じたことのあるエピソードを3つ紹介していきます。
エピソード1: ドラマの途中で感じるモヤモヤ

ドラマの一話が終わるとき、クライマックスで「続く…」となった瞬間、次回が気になって仕方がなくなることはありませんか?特に、物語の核心に触れそうなシーンで終わられると、「どうなるんだろう?」と興奮が冷めやらないまま次のエピソードを待ち望むことになります。
このような「続きが気になる」という心理状態こそ、まさにツアイガルニック効果の影響です。制作側はこの効果を巧妙に利用して、視聴者を次のエピソードに引き込もうとしています。この効果のおかげで、私たちは物語にどっぷりとハマり、毎週欠かさず視聴することになるのです。
エピソード2: 途中で途絶えたプロジェクト
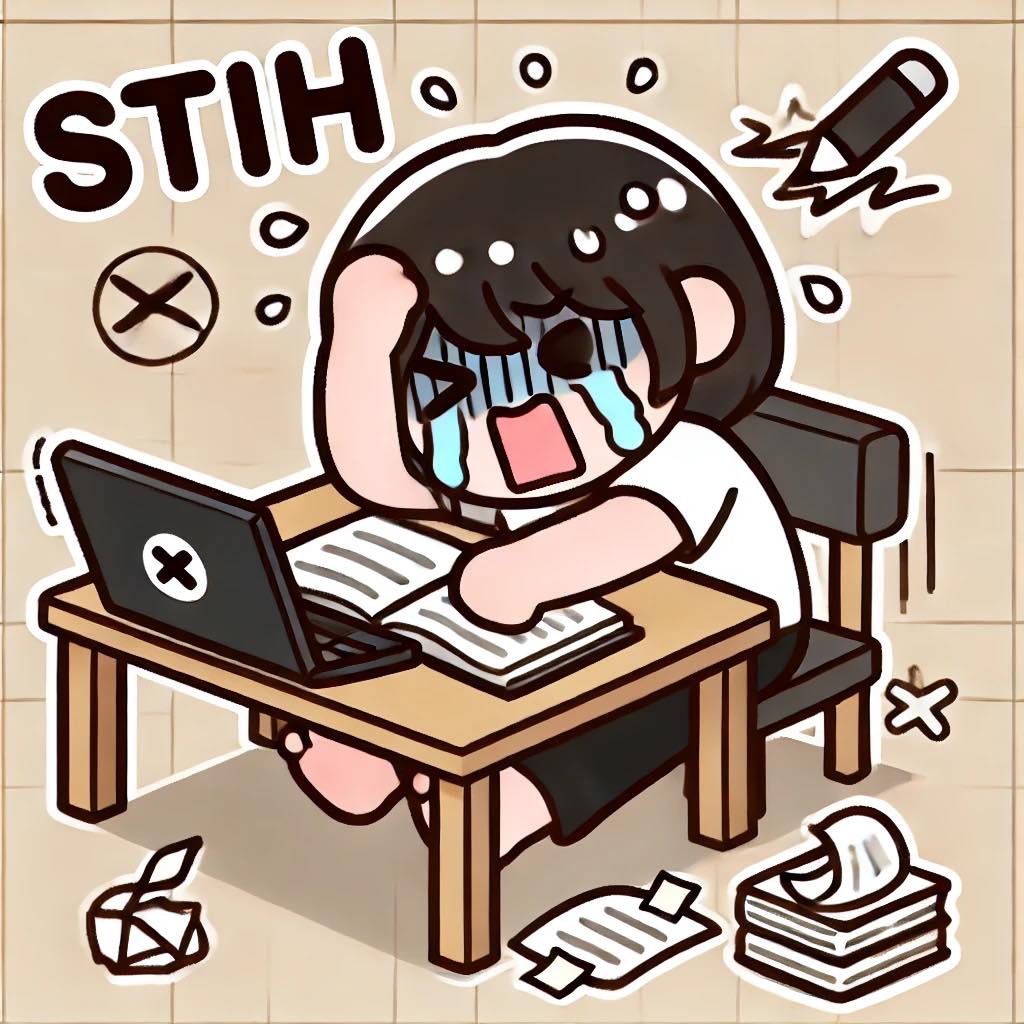
仕事でプロジェクトに取り組んでいる最中に、上司やクライアントの要望で一旦中断せざるを得なくなることがあります。中途半端な状態で中断されたプロジェクトは、完了させることができなかったために、頭の中からなかなか離れません。
結果として、その未完了の状態がストレスを引き起こすこともありますが、逆に「早く終わらせたい」という強い動機付けに変わることもあります。この「終わっていない」という認識がツアイガルニック効果を通じて、仕事への集中力やエネルギーを高める要因になるのです。
エピソード3: 勉強の途中で止めることで記憶を強化
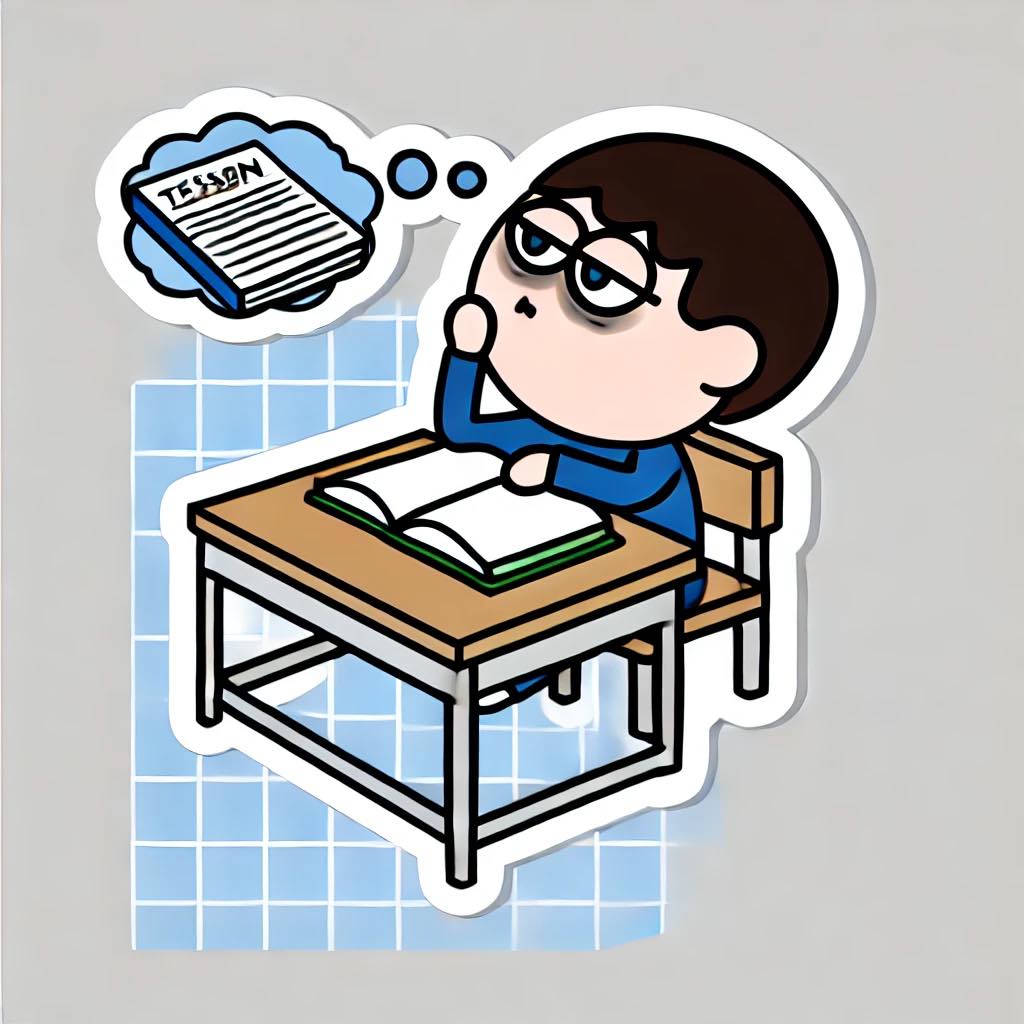
学生時代、試験前の夜に勉強をしていて、時間切れで途中までしか学習できなかったことはありませんか?その未完了の状態で一晩寝た後、翌日その部分が頭に残っていて驚いたという経験があるかもしれません。
実は、ツアイガルニック効果は学習においても有効です。特に、新しい知識やスキルを学んでいるときに、敢えて途中で中断することで、その未完了の内容が脳に強く残り、次に取り組むときの理解が深まることがあります。途中でやめることで、記憶を強化し、次の学習へのモチベーションを維持することが可能です。
ツアイガルニック効果のメリットとデメリット
ツアイガルニック効果のメリット
ツアイガルニック効果を上手に活用することで、未完了のタスクに対する関心を維持しやすくなり、モチベーションを持続させることができます。例えば、仕事や学習において「少しだけやってみよう」と取り掛かることで、途中で止めたことが気になり、自然と次に進みやすくなるのです。また、プロジェクト管理においては、適度にタスクを分割して完了させずに置くことで、効率的に進行する手助けにもなります。
一方で、創作活動などのクリエイティブなプロセスにおいても、ツアイガルニック効果は有効です。アイデアを途中まで温めておくことで、脳が自動的に背景でそのアイデアについて考え続けるため、次に取り組む際に新たな視点やインスピレーションを得ることができるからです。
ツアイガルニック効果のデメリット
一方で、ツアイガルニック効果にはデメリットも存在します。未完了のタスクが頭の中に残り続けることで、ストレスや不安感を引き起こすことがあるのです。例えば、複数のプロジェクトが同時進行している状況では、それぞれが中途半端な状態であることで精神的な負担が大きくなり、集中力を奪われてしまうこともあります。
さらに、未完了のタスクに対する執着が強くなると、休息を取ることが難しくなったり、リラックスする時間が減少してしまう可能性もあります。そのため、ツアイガルニック効果を有効に活用するには、適度な休息を取ることや、タスクの優先順位を見直すことが重要です。
ツアイガルニック効果を活かすための具体的な方法
ツアイガルニック効果を日常生活や仕事に取り入れるための具体的な方法をいくつか紹介します。
- タスクを細かく分割して中断する: 大きなタスクを小さな部分に分割し、途中であえて中断することで、次に取り組む際のモチベーションを高めることができます。例えば、長時間かかるプレゼン資料の作成を「資料の構成を考える」「必要なデータを集める」「スライドをデザインする」などに分け、それぞれのフェーズで意図的に止めることで、次の作業にスムーズに取りかかれます。
- リマインダーを活用して未完了感をキープする: ツアイガルニック効果を活かすために、タスクの途中でリマインダーを設定しておくのも有効です。これにより、未完了のタスクが適度に思い出され、自然と再開する気持ちを持ち続けることができます。
- 「ちょっとだけ手を付ける」戦略: 大きな仕事や手をつけるのが億劫なタスクに対して、「ほんの少しだけやる」というアプローチで取り組んでみましょう。例えば、「5分だけ資料を読む」「メールを1通だけ返す」といったように、始めることで次第に勢いがつき、途中で中断したことが逆に次の行動を促す力になります。
まとめ
ツアイガルニック効果は、未完了のタスクや中断された物事を強く記憶に残す心理効果です。この効果をうまく利用することで、仕事や学習、生活の中でのモチベーションを維持しやすくなります。ただし、未完了の状態がストレスや不安を引き起こすこともあるため、上手にコントロールしながら活用することが大切です。
20代から30代の会社員の皆さんは、日々多忙な中で多くのタスクを抱えていることでしょう。ツアイガルニック効果を理解し、うまく取り入れることで、次の行動への原動力を生み出し、効率的に仕事を進める助けになるかもしれません。少しの工夫で、未完了を「やる気の種」に変えて、日々のパフォーマンスを向上させていきましょう。

